ペポー

ペポーは、かつて日本で栽培されていたジャガイモの品種です。
かつては作付面積の18%も占めていたというペポーは、
どのような特徴を持っているのでしょうか。
[ペポー]
・登録年 1929年
・登録番号 Pepo
・作型 春作、秋作
・主な産地 北海道
・特性 煮崩れせず粘質
・栽培難易度 中級
■ペポーの特徴
・ドイツ生まれのジャガイモ
ペポーは、もともとドイツで育種されたジャガイモです。
多収の性質があるため、栽培すれば多くのイモが収穫できるのですが
食味がいまいちということで、ドイツでは豚用の飼料として栽培されていました。
日本には1924年頃に入ってきて、優良品種として認定され、
栽培が続けられました。
ところが、ペポーを元に交配した品種「紅丸」が登場してからは、
そちらの方が性質が良いということで、急速に栽培面積が狭くなり、
1959年には優良品種からも登録がはずされました。
・つるりとした見た目
ペポーは、やや細長い楕円形をしているのが特徴です。
表面の皮は黄色で、中の肉色は白です。
目がやや浅い上に、表面の皮が滑らかなため、
つるりとしていて見目が良いです。
目は浅いだけでなく、数もそれほど多くないので、皮を剥くのが容易です。
・微妙な食味
ペポーは収量も期待できて、見た目も悪くありません。
それでも栽培されなくなったのは、食味が微妙なためです。
もともとドイツでも食味が悪いため、
豚用の飼料として栽培されていたほどです。
日本人にとってもペポーの食味は良いとはいえませんでした。
それでも栽培していたのは、デンプン加工品の原料として使うためでしたが、
後に出てきた紅丸の方が良質のデンプンがとれるということで、
栽培されることはなくなりました。
■ペポーの栽培のポイント
・標準的な株姿
ペポーの株姿は、日本で栽培されている標準的なジャガイモとよく似ています。
やや開帳気味に茎が開くものの、茎の長さや本数、
葉の大きさなどが特別変わっているということはありません。
中晩生タイプの性質なので、収穫のタイミングも難しいものではありません。
・冷涼な気候を好む
ペポーはドイツで改良された品種のためか、
暖地よりも冷涼な地域の方が収量が上がり、質の良いイモが収穫できるようです。
二次生長が出やすい品種のはずですが、北海道東北部で栽培されていた時には、
ほとんど二次生長が出ることがなかったそうです。
そのため、北海道の東北部ではペポーという名前ではなく、
天塩薯と呼ばれていました。
・過度な排水に注意
ペポーは、少し乾燥に弱い性質があります。
そのため、過度に乾燥させると褐色芯腐の症状が出やすくなります。
極端に排水の良い土での栽培は避け、
緑肥植物をすきこんだりして水もちを良くした土で育てるようにします。
また、種芋を植え付ける際には、少し深めに植え付け、
しっかりと覆土しておくことも乾燥を防止には重要です。
■ペポーのオススメの食べ方
デンプン加工原料として栽培されていたため、
調理に使うことはほとんどありません。
デンプン価が低いので、煮崩れしにくく加熱後の肉色の変色も少ないです。
食味の悪さを補うため、味の濃いシチューやカレーのような煮込み料理になら、
使えるかもしれません。
■参考
・ジャガイモ 地植えの栽培
・ジャガイモ プランターの栽培
・ジャガイモ 芽かき方法
・ジャガイモ 土寄せ方法
・ジャガイモ タネイモ販売
・ジャガイモ タネイモの選び方
プレバレント

プレバレントは、オランダで育種されたジャガイモの品種です。
日本のスーパーなどでは、あまり見かけることのない品種ですが、
プレバレントはどのような特徴と栽培のポイントがあるのでしょうか。
こがね丸

こがね丸 C)春夏秋菜
こがね丸は、ムサマルと十勝こがねを親に持つ、ジャガイモの品種です。
親の性質を存分に受け継いだこがね丸には、どのような特徴があるのでしょうか。
また、栽培のポイントやオススメの食べ方もご紹介します。
シマバラ

シマバラは、春と秋の2回栽培できるジャガイモ品種です。
現在はほとんど栽培されていないというシマバラには、
どのような特徴があるのでしょうか。
また、栽培のポイントや相性の良い調理法なども、合わせてご紹介します。
チェルシー
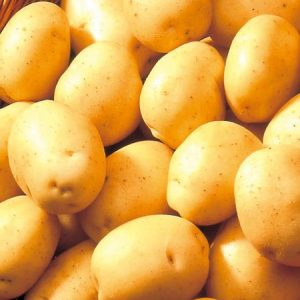
チェルシー
チェルシーは、海外生まれのジャガイモ品種です。
つるりとしていて美しい見た目は、美の国フランスならではです。
そんなチェルシーの特徴や、栽培のポイントなどをまとめました。
